2025年度 住環境デザインレビュー
2026年2月17日(火)【イベント, 授業の様子】
奈良女子大学、大阪公立大学、京都府立大学、摂南大学の住環境系学科が合同で行う2回生設計演習 集合住宅課題の講評会です。
どなたでもご参加いただけます。
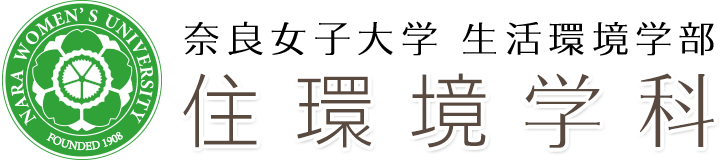

奈良女子大学、大阪公立大学、京都府立大学、摂南大学の住環境系学科が合同で行う2回生設計演習 集合住宅課題の講評会です。
どなたでもご参加いただけます。
「住居デザイン学」では住居を中心に建築のデザインの理論や実践を座学で学ぶ授業です。学外見学では、建築家の安藤忠雄氏設計の「日本橋の家」の見学に行きました。
建築材料学は、1回生を対象に後期に開講しています。建築物を構成している主な材料(木材、鋼材、コンクリートを中心に)について基本的な性質について概説します。また、部位別に建築材料に求められる性能について説明し、適材適所な使い方について考えていきます。
まちづくり演習Bでは、本年度は、奈良県の重要伝統的建造物群保存地区のひとつである宇陀市松山で授業実施しました。来年に重伝建地区選定20周年を迎えるプレイベント(松山夢街道:8月28日~30日)の企画のひとつとして、かつてのまちなみの古写真収集をしました。
大学院の生活空間計画論演習では、京都工芸繊維大、近畿大、大阪公立大、龍谷大、大産大、岡山県立大など、関西を中心とした建築系・住居系の意匠系研究室と連携して、「都市アーキビスト会議」と名乗って連携授業をしています。2022年には、「日本建築学会教育賞(教育貢献)」も受賞しています。テーマは、これまで3年ごとに、宿泊施設、駅、都市のコアと移り変わり、今年からは新テーマ、なんと「都市の恋愛空間」に取り組みました。
2年生前期から設計演習が始まりましたが、前半が独立住宅で、後半がテナントビルでした。授業の最終回に、テナントビルの完成作品の講評会を実施しました。 昨年同様、敷地は、JR奈良駅前から猿沢池、春日大社参道まで店舗がならぶ三条通の一角で、商業ビルの設計をしました。
建築設備学は、3回生前期に開講される科目です。建築設備とは、建物を使う人々の快適性、安全性等を保証するために実装される機械・設備のことです。例えば、トイレ、エアコンなどがこれに該当します。
3回生前期の住環境工学実習内で取り組む課題の一つ「微気候計測」を紹介します。皆さんは、気候という言葉からはどの様なイメージを抱きますか?
2月7日卒業設計発表会(オープンジュリー)が、ランドスケープアーキテクトの平賀達也さん、建築家の中山英之さん、金野千恵さんをお招きして、開催されました。
住環境学科では、半年に1回、1回生から3回生までの設計演習の優秀課題を3学年合同で講評会を行っています。
今回は、一回生はキャンパス内の小さな居場所、二回生は、①タウンハウス、②奈良町の小公園、三回生は、①市内の団地の建て替え・跡地計画、②特別養護老人ホームの合同講評会でした。