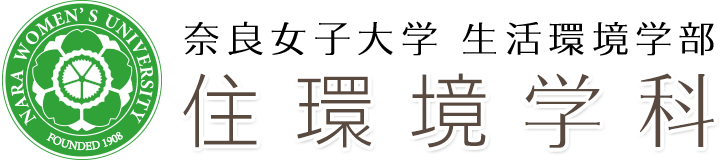2019年11月2日に2019年度の第2回オープンキャンパスを開催いたしました。
7月のオープンキャンパスより参加者はやや少なくなりましたが、多くの方に参加いただきました。
住環境学科では、学科説明会、3回生の設計演習課題の公開講評会、設計演習、卒業設計の展示。CAD作品の展示、光・温熱環境の測定体験、建築構造・木質材料の説明、土建築の紹介などのプログラムが実施されました。
御来場の皆様、ありがとうございました。

2019年10月17日(木)【お知らせ, イベント】
住環境学科主催で、「人生フルーツ」の登場人物である津端氏と舞台となる高蔵寺ニュータウンにまつわる講演会および映画上映会を開催します。どなたでも参加いただけますので、ご興味のある方はぜひ足をお運びください。

2019年9月16日(月)【授業の様子】
8月9日に、学部2回生から4回生までの設計演習の合同講評会を、各課題から優秀作品を3課題ほど選抜して行いました。
2回生は、キャンパス内のランドスケープ、壁式構造の独立住宅、ラーメン構造によるテナントビル、3回生は、中高層集合住宅、法隆寺の宝物展示施設、4回生は奈良公園を敷地に建築とランドスケープを融合したオーベルジュの設計課題でした。
ゲストクリティックには、京都造形芸術大学から城戸崎和佐先生(建築)と長谷川一真先生(ランドスケープ)、AN Architects一級建築士事務所の長澤浩二先生にお越しいただきました。

2019年7月27日に2019年度第1回オープンキャンパスが開催されました。台風が近づき天候の悪化するなか、多くの方に足を運んで頂き賑わいました。
住環境学科では、学科説明会、2回生の設計演習課題の公開講評会、設計作品展示、光・温熱環境の測定体験、建築構造・木質材料の説明、土建築の紹介などのプログラムが実施されました。
2019年7月 5日(金)【お知らせ, イベント】
2019年7月27日(土)にオープンキャンパスを開催します。住環境学科では、学科説明会、2回生の設計演習課題の公開講評会、設計作品展示、光・温熱環境の測定体験、建築構造・木質材料の説明、土建築の紹介など学科での学びが感じられるプログラムを準備してお待ちしています。

理系女性教育開発共同機構 長田直之准教授(元住環境学科教員)が顧問として、本学住環境学科学生と、関西の4大学(大阪芸術大学、大阪工業大学、近畿大学、滋賀県立大学)が奈良県川上村をフィールドとして活動する「川上村木匠塾」が2019年度日本建築学会教育業績賞を受賞しました。

奈良女子大学創立 110 周年を迎えるにあたり、奈良女子大学学生寮の一部を建て替えます。この建設に向けて、2018 年4月からワーキンググループが発足し活動をしています。普段の学生ミーティングに加え、大学や行政機関の協力を得ながら、授業の課題とは違った実務的な設計に取り組んでいます。現在、住環境系の学生が中心の活動となっていますが、今後活動の幅を広げていきたいと考えています。
2019年5月16日(木)【学生の表彰】
宮内(城戸)杏里さん(平成30年3月博士課程修了)が、今年度の日本建築学会奨励賞(40才未満の学会論文賞)を受賞しました。本学博士課程修了者では初めての受賞で、9月の建築学会大会で受賞式が行われます。受賞論文名と受賞理由は、次のようです。
屋敷神の礼拝圏と職業姓の分布から見た都市型住居の平面類型とその発展過程 ネパール・バクタプルにおける生活空間と都市組織に関する研究 その2 日本建築学会計画系論文集第82巻第741号/pp.2843-2853/2017年11月

2019年4月26日(金)【学外研修】
2019年4月19日(金)~20日(土)に新入生合宿研修を行いました。金曜日は夕方に大学近くの奈良ユースホステルに集合し、みんなで夕食を食べたのち、学科ごとに交流しました。人生の大事件を元にキャッチコピーを考えあう自己紹介タイムはとても盛り上がり、教員も含めてお互いに人がらを知る機会になりました。

2019年4月17日(水)【授業の様子】
京都造形芸術大学大学院教授で建築家の岸和郎先生(京都大学・京都工芸繊維大学名誉教授)をゲストにお迎えし、1回生から3回生の授業作品を講評していただきました。
光の箱(1回生)、奈良町の猿沢池を臨むランドスケープ(2回生)、住宅地に建つ特別養護老人ホーム(3回生)など、合わせて5課題の優秀作品の発表でした。